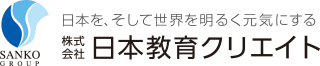入職者の受け入れ~組織社会化~
目次
ドキドキの転校生
私は、幼い頃から2、3年に一度は父の転勤で引越ししなくてはならず、小学校を3校、中学校を3校、高校も3校転校をしました。人見知り等という余裕もなく、慣れるとか慣れないとかそんな次元でもなく、「今日を生きる」ためには、新しい環境に目をつぶって飛び込むしかなかったわけですが・・・(笑)。
初めての土地、学校、初めての先生、初めてのクラス・・・その都度結構大変な不安を感じていました。転校は、毎回初めて海外に一人で行くようなもので、巨大迷路の中にひとり放り込まれる様です。帰りに友達とはぐれたら最後、靴を履き替えて帰ろうにも下駄箱の場所も位置もわからなくなるし、帰り道も家まで迷わず無事に帰りつくかドキドキです。
ドキドキは、初日1日で終わるはずもありません。先生やクラスメイトの顔はもちろん、職員室や理科室、保健室などの位置を覚えることは、その後の毎日の学校生活の生命線です。初日のうちに覚えないと広―い校内でたくさんの生徒や先生がいるにもかかわらず、あっという間に親のいない「迷子」になってしまいます。
受け入れ側の免疫反応
一方、受け入れるクラスメイトにとっても、転校生はものすごく珍しい新生物です。心の中は大興奮状態!転校生は今までの「居心地の良い日常」に良くも悪くも変化を起こす「異質な存在」。免疫機能がマックスに働いて、何とかしてこの素性の分からない新生物を解明しようと試み、様々な試練を課します。
転校生の頭の中は、ただでさえ顔認証システムと現在位置確認システムがくるくる回っているこの時期に、初日から上履きがなくなる、理科室では座る椅子がない、クラスに戻る際に全員に走って逃げられた時には、もはや戻るクラスの方角も場所もわかりません。今思うにこの洗礼で、新入りがどの程度の対応力があるのかが試されていたのではないかと思います(笑)。
しかし、これがまた有難いことに、必ず1人、2人、待っていてくれる心優しい「天使」がいたりします。それはもう涙が出る程ありがたくて、一度手を握ったら教室に戻るまではその手を離したくなくなります。
ハードルの高いチャレンジ
転校翌日からも「日常」は続くわけで、日直、委員会、給食の配り方、休み時間の過ごし方・・・様々なことが前の学校とは微妙に違います。聞けばいいじゃないと思うのですが、発言や質問などはハードルの高いチャレンジ。少しでも目立てば「生意気」だといじめの対象になりかねない。そのタイミングはかなり難しいものです。だからと言って謙虚におとなしくして、もたもたしていると、本来は全員が食べられるはずの給食にすらありつけないこともあります。先程の天使ですら、この微妙な違いや塩梅については教えてくれません。
当然です。彼らにとって「日常の当たり前」、私が戸惑っている理由が何なのかは想像もできないし、戸惑っていることすらわからないのです。
「新しい組織に入る」とは、そういうことです。
外からしか見えない壁
現存する組織には、外から来たものにしか感じられない「暗黙のルール」や「漂う空気」が存在します。それは眼に見えないハッキリしない曖昧なもの。しかし、とてつもなく強固で「やっかいな」ものです。「新入り」は、それらを自ら学習して、いち早くその新しい組織に馴染んで「適応」していかなければなりません。上手く適応できなかった場合には、そこでの居場所はなく、いろんな形で最悪その組織を離れざるを得ない状況になってしまうこともあるでしょう。
最近、新卒者入職3年未満の離職が人事の大きな問題になっています。そこには、ダイバーシティ、キャリアに関しても多様な価値観があることに加え、このような「適応」の問題が潜んでいます。新しく組織に加わったメンバーが、その組織の共通の目的、価値観、目標達成のための個々の役割を学習しながら、その組織に馴染んでいくプロセスのことを「社会組織化」と言います。
新入りが戦力になるには・・・
「新入り」「転校生」が、どうすればそのクラス(組織)に馴染んでうまくやっていけるようになるのか、その人本来の実力を発揮できる状態になるのか。
そのためにクラスメイトや先生には何ができて、また転校生自身には何ができるのか。
これが「定着管理」です。
採用すれば終わりではありません。研修さえすれば、翌日から途端にバリバリ業務ができるわけでもありません。
「新人を1日でも早く戦力にする」そうすれば、いずれは中堅、ベテランさんも楽になり、仕事のクオリティも上がっていきます。「使えない」お荷物的存在として排除するか、受け入れていち早く育て上げるか。それは、受け入れる職場の意思にかかっています。
今日、今の時点でできないのは、バカでも使えないのでもなく、ただ知らないことが多く経験値が足りないだけです。顔認証システムやGPSが機能し始めて、本当の業務機能が動き出すまでは「入る方」も「受け入れる方」も、待ちましょう。「3分間、待つのだよ・・・」そんなコマーシャルが昔ありました(笑)。
新人教育などは、組織社会化を促進するための活動の一部。実は、受け入れる所属、上司、先輩職員の対応=「環境創り」が一番大切なのです。
筆者紹介

私たちの目指す研修
社会の根本であるコミュニケーションに着目し、行動心理学や思考分析ツールを通して「人や組織が問題を乗り越え、自分らしく活き活きと幸福感を持って過ごす」事が出来る様、コンサルティングや研修等を行なっています。人生の悩みの殆どは「人間関係」。社会は様々な考えや感情、価値観を持ち、違う人生を歩む人々の集まりです。「人との関わり=コミュニケーション」は欠かせないものであり、「質の良いコミュニケケーション」をとるスキルは必要不可欠です。また、内発的な感情・欲求により、人は行動し前に進むことが出来ます。個人や組織の内面にアプローチし、自律進化型思考の人財を育成、自発的永続的に活性化する組織を創ります。仕事を単なる「作業」ではなく、やりがいや存在意義のある「お志事」に!働く事そのものを歓びに!