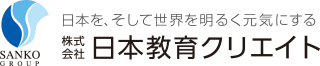若手職員が「ぐんぐん育つ」組織とは
目次
前回は、時代の変化によって仕事に対する向き合い方も変わってきているということをご紹介しました。
今回は、「どのように若手職員が育つ組織を作っていくのか」についてご紹介します。
キーワードは「試行錯誤できる環境」です。
人から注意されることに慣れておらず、正解は調べればすぐにわかるので、「わからない」ということに悩む経験も少ない若手職員。
そのような中で、「失敗する」という経験が若手職員にはとても高いハードルになっています。
だからこそ、自分から、今までの方法や考え方を覆し、新しいことに挑戦する、改善点に気付き、自分から行動するということがなかなかできなくなっています。
つまり、若手職員を育てていくためには「失敗できる環境」が必要です。
もちろん、医療・介護・保育の現場は、人の命に係わる重要なお仕事です。失敗が許されない仕事が多くあると思います。
仕事の失敗をすべて許すことが必要なのではありません。
「失敗できる環境」に必要な要素がある職場環境を作っていくことが、管理職には求められています。
失敗をするためには、新しいこと、取り組んだことがないことに挑戦をさせなければなりません。
その挑戦を引き出すためには、「何があっても受け止めてもらえる安心感」が必要です。
「失敗しても、あの上司はフォローしてくれる」
「上司は自分のやりたいことをわかってくれていて、相談に乗ってくれる」
「自分が困った時に助けてくれる仲間がいる」
このような心理状態であると、挑戦へと意識を向けることができるのです。
では、上司として何をするべきか。それは、悩みを相談しやすい上司であることです。
自分の思っていることや感じていることを受け止めてくれる、理解してくれる人のほうが話しやすいということはみなさんも経験上あるのではないでしょうか。
アドバイスをどんどんしてくれる、教えてくれるのではなく、「気持ち」や「考え」を理解してくれる、いわゆる受信型のコミュニケーションが求められています。
しかし、若手職員の話ばかり聞くわけにはいきません。
注意・指導の際に若手の納得感を引き出すためには、その目的・意味が納得できるように伝えていくことが重要です。
「自分が若手の頃はこうだったから」「このやり方のほうが正しいから」と一方的に押し付けるだけでは、受け身の職員しか育ちません。
若手職員は、なぜそれをやる必要があるのか、そこに納得感を持つことができ、挑戦できる環境があれば、ぐんぐん成長していくことができます。
ぜひ管理職の皆さんの若手職員の成長に向けて「挑戦」してみましょう。
筆者紹介