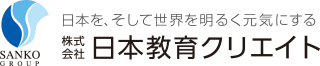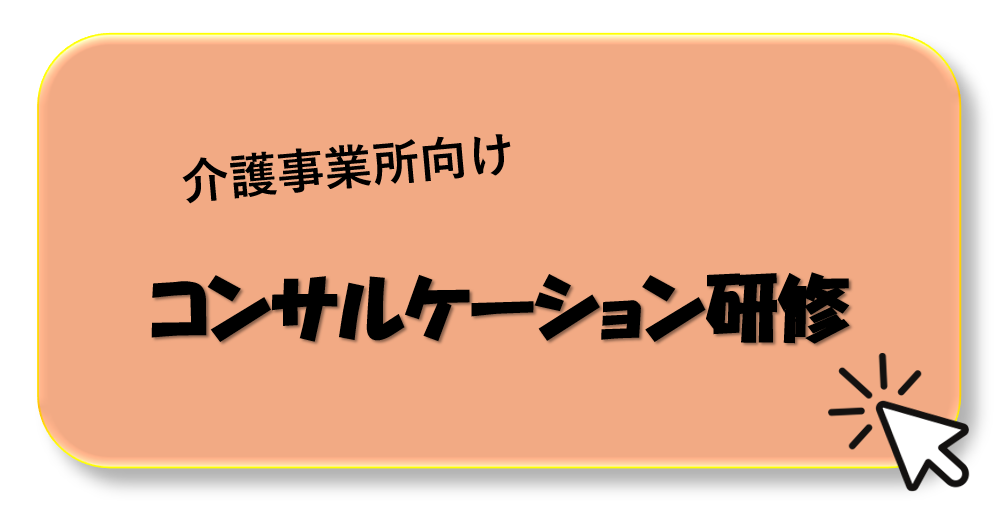医療と介護の連携とは?地域包括ケアを支える仕組みと実践例を解説
目次
医療と介護の連携とは?
厚生労働省の資料によると、医療と介護の連携は住み慣れた地域で、必要な医療や介護サービスを継続的・一体的に受けられる「地域包括ケアシステム」の構築のために必要不可欠なものと定義しています。
医療と介護の連携は、高齢化が進む現代社会において、患者や利用者が住み慣れた地域で安心して生活を続けるために非常に重要です。
それは単なる情報共有ではありません。医師、看護師、介護福祉士、セラピストなど様々な専門職が連携することで、利用者の状態を多角的に把握し、より適切なケアをチームで提供することが出来るのです。
専門職がそれぞれの知識や技術を活かして、利用者の自立を促し、生活の質を向上させるなど、一人一人のニーズに合った個別のケアの実現に繋がります。
医療・介護連携が求められる背景と社会的課題
なぜ今、医療・介護の連携が求められているのでしょうか。
現代の日本社会においては、世界でも類を見ないほどのスピードで高齢化が進んでいます。
2025年、団塊の世代全員が75歳以上になり後期高齢者の増加が急増しています。
このような背景から、医療と介護の両方を必要とする人が増えて、医療・介護サービスの需要が爆発的に高まっています。
ところが医療・介護資源の分布は地域によって偏りがあり、比較的都市部では充足してはいるものの、地方や郊外においては不足傾向にあります。
このため、地域によっては十分な医療・介護サービスを受けられない状況です。
また、高齢化に伴う需要増に対して、医療・介護人材の不足は深刻化を増しています。
特に地方や郊外では医療機関や介護施設の数が限られており、十分なサービスを提供することが困難な状況です。
また、高齢化や医療技術の進歩により、疾病構造や患者のニーズが変化したため、これまでの病院完結型から地域完結型医療への移行が進んでいます。
入院期間の短縮化、退院後の生活を支えるための地域連携の必要性からも進められています。
特に入退院支援の複雑化は、病院だけではなく地域の医療・介護関係者との連携を不可欠にしています。
医師・看護師・介護福祉士・薬剤師・理学療法士などの他職種が連携して、患者の状態やニーズに合わせた包括的ケアの提供は避けて通れません。
地域完結型医療への転換は、高齢化社会における医療提供体制の重要な課題であり、地域全体で取り組むべき課題です。
*厚生労働省発表より65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測(3,878万人)https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/zaitakuiryou_all.pdf
在宅医療を必要とする者は2025年には29万人と推計され、約12万人増えることが見込まれる。https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/h24_0711_01.pdf
連携が必要とされる4つの主な場面
ここでは、医療・介護の連携が必要とされる主な4つの場面について述べていきます。
退院支援時(入退院時カンファレンス)
患者や家族が、患者の病状、治療経過、退院後の生活に必要な情報(医療処置、リハビリ、服薬、介護サービスなど)を医療機関(医師・看護師・退院調整看護師・医療ソーシャルワーカー・薬剤師・リハビリスタッフ)と在宅サービス(ケアマネージャー・訪問看護師・訪問リハビリスタッフ・訪問介護員・かかりつけ医・薬剤師など)、そして必要に応じて福祉用具相談員・地域の相談支援専門員などと、退院後の生活に不安を抱えることなく、安心して療養生活を始められるように共有します。
訪問診療・看護とケアマネ連携
患者が安心して在宅療養を継続するために、訪問診療における看護とケアマネジャーの連携は不可欠です。
ケアマネジャーは、患者の心身の状態や生活環境・家族の状況を把握し個別の患者ケアプランを作成します。また訪問看護ステーションを含む様々な介護サービス事業者と連絡調整や、必要なサービス手配を行います。
そして定期的な情報交換や、必要時の連絡を密に行い、患者の状態やケアプランの進捗状況を共有します。
訪問看護師は、このプランに基づいて必要な看護サービスを提供します。
急変時の連絡対応(看取り・救急)
医療機関と介護施設・事業所は、患者・利用者の病状、治療方針、生活状況などの情報を共有し連携を密にすることが重要です。
情報連携シートを活用して、スムーズな情報共有を図ることが推奨されています。
見取り介護においては患者・利用者・家族の意向を尊重し、慰労・介護関係者が連携して安心出来る療養環境を整えることが重要です。
介護施設や在宅での療養中に急変が発生した場合、速やかに医療機関へ連絡し、指示を仰ぐことが求められます。救急現場では、消防隊と救急隊が連携して救急活動を行うPA連携が重要です。
定期的なサービス調整(モニタリング)
ケアマネジャーが、ケアプランに沿って介護サービスが適切に提供されているかということを定期的にモニタリングとサービス調整を行います。必要に応じて調整したケアプランは、医師、看護師、理学療法士、作業療法士など専門職と連携して、情報を共有します。
地域包括ケアシステムとは?
地域包括ケアの理念とは、高齢者が住み慣れた地域で、人生の最後まで自分らしい暮らしを続けられるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援を一体的に提供する体制を構築することです。
厚生労働省が推進する「在宅医療・介護連携推進事業」は、高齢化社会で医療と介護の両方を必要とする人が地域包括ケアシステムの構築により、住み慣れた地域・自宅で自分らしく生活が出来ることを実現する取り組みです。他職種協働により、在宅医療や介護を一体的に提供できる体制を構築する為に、市町村や都道府県が地域の自主性や主体性に基づいて、地域の医師会と密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制の構築を推進するものです。そして、日常の療養支援、入退院支援、緊急時の対応、見取りの4つの場面を意識したPDCAサイクルに添った取り組みを目指しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001468173.pdf
以下に、いくつかの事例を紹介します。
〇自治体が設置する連携相談窓口の例:
仙台市
https://www.city.sendai.jp/kaigo-suishin/iryou_kaigo.html
千葉市
https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/shien/ikairenkeisoudanmadoguchi.html
〇連携支援会議例:
小平市
https://www.city.koganei.lg.jp/kenkofukuhsi/koreishafukushi/zaitakuiryoukaigoren/renkei.files/R01.1_shiryou.pdf
島根県:(YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=61e3zia_Q60
医療と介護の情報共有
医療と介護の情報共有は、多職種連携を円滑に進め、患者・利用者への適切なサービス提供に不可欠です。
現場において使われる情報共有の手段や課題には以下のものがあります。
[対面カンファレンスによる口頭での申し送り]
ニュアンスが伝わりやすい/ その場でコミュニケーションが図れる/ 伝達漏れや聞き間違のリスクがある。
[書面での申し送り]
記録で残り正確性を高められる/ 手書きの場合、読みにくさや情報が整理されていないことがある
- 電話
急を要する連絡に適している/ 口頭での詳細な説明が出来る/記録で残せない - ICT(多種職連携アプリ)
電子カルテの共有、オンライン診療、遠隔医療、AI診断/ 患者情報の共有ができるため、より適切な医療・介護を提供できる/ コストがかかる/ ITリテラシの不足/ セキュリティア対策の必要性/ コミュニケーション不足 - 医療・介護連携シート
医療機関と介護事業所が情報共有や連絡調整を円滑に行うためのツール/ ケアマネジャーが作成したケアプランや、入院・退院時の情報などを共有できる/ 情報伝達の正確性の必要性(簡潔・わかりやすさ)
<参考>
荒川区と長野県では、医療と介護の連携を強化するために「医療と介護の連携シート」が活用されています。
荒川区:医療と介護の連携シートについてhttps://www.city.arakawa.tokyo.jp/a028/koureishairyou/koureishairyou/iryoutokaigorennkei.html
長野県:医療と介護の連携について
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/documents/documents/iryou-kaigo-renkei1.html
- FAX
紙ベースでの情報共有が出来る/ 緊急時や情報が限られている状況下で、迅速な手段となる場合/ 情報漏洩のリスクがある/ セキュリティリスク対策の必要/ 誤送信の注意
医療と介護の連携がうまくいかない主な原因
医療と介護の連携には上手くいかないケースもあります。その場合の主な原因を以下に紹介します。
情報共有の不全
情報共有の不全が連携を阻害することがあります。
情報伝達の遅延、異なる職種間での情報共有の困難さ、連携する医療・介護機関の間での情報格差があります。
その具体例として以下のことが挙げられます。
- 医療機関で得られた患者の病状や処方に関する情報が、難しすぎたり、介護施設にタイムリーに伝わらず、介護スタッフが適切なケアを提供できない。
- 医師が患者のリハビリテーションの必要性を認識していても、リハビリテーション専門職にその情報が伝わらず、リハビリテーションが遅れてしまう。
職種間の価値観の違い
医療職は、診断や治療といった医療行為を優先する傾向がある一方で、介護職は日常生活の支援や生活の質(QOL)の向上を重視する傾向にあります。こういった「何を優先すべきか」が異なることから様々な摩擦が生じることがあります。
具体例として、終末期医療において治療方針を決定する際に、医療職は、延命を目的とした積極的な治療を提案する一方で、介護職は患者の意思やQOLを考慮し、緩和ケアを提案することがあります。
このような価値観のギャップによる摩擦を防ぐために、共通理解の醸成が必要で、医療職と介護職が、患者のQOLや生活を尊重するという共通の価値観を持つことが重要です。そのために、研修を活用して医療職と介護職が、互いの専門性や役割を理解し共通の目標に向かって協力する体制を構築することが大切です。
制度やICTの未整備
医療と介護の連携において、電子カルテと介護記録の非連携が、情報共有の遅れや業務効率の低下を招き、その結果として患者・利用者のケアの質に影響を与える可能性があります。
そういった中において、個人情報保護に対する過剰な遠慮の意識から、必要な情報共有をためらうケースが見受けられます。例えば、緊急時の連絡や、介護サービスに必要な情報共有をためらうことにより、連携不足を招き、結果的に患者の安全が脅かされる可能性があります。適切な情報共有と個人場保護の両立が重要です。
また、医療と介護の連携をFAXに頼るといった、時代に合わない現場も依然と多いのが現状です。これはFAXの送受信や内容の確認、記録など手作業による手間が多く、業務効率を低下させる原因となります。
加えて情報伝達の遅延やセキュリティリスク、情報の一元管理の困難さなど多くの問題を抱えています。
ICT(医療現場における、電子カルテ・オンライン診療・遠隔医療・医療情報の共有など)を活用した連携に移行することにより、より効率的で安全な情報共有が可能になり、質の高い医療・介護サービスを提供できるようになるため、連携が求められています。
医療・介護連携をうまく進めるための工夫と解決策
これまでに、医療と介護の連携の必要性やその主な場面について述べてきました。
その中で、連携が上手くいかない原因についても紹介しました。
ここでは、連携を上手く進めるための工夫と解決策について記述します。
ルールと共通言語を整備する
医療と介護の連携の前提となる「連携ルール」、特に共通用語の共有は、医療・介護従事者間の情報伝達をスムーズにし、患者、利用者へのより質の高いケア提供において不可欠です。
医療と介護の現場で同じ言葉で情報を共有することは、誤解や認識のズレを防ぎ、スムーズな情報伝達が可能になるためにとても重要です。
顔の見える関係性を構築する
「顔の見える関係性」とは、医療・介護の関係者が、お互いの専門性や人となりを理解して、気軽に連絡を取り合えるような良好な関係を築くことです。
例えば、定例の合同カンファレンスや地域連携会議、研修会などを医療・介護関係者が集まる機会を設け、顔合わせや情報交換などをすることにより、「この人に聞けば早い」といった関係づくりがとても重要です。
ICT活用と現場教育の両立
医療と介護の連携におけるICT活用は、情報共有の効率化、業務効率の向上、そして患者へのより質の高いサービス提供に繋がるため、ツールの導入は地域包括ケアシステムの構築において不可欠です。
ポイントは、導入だけではなく「どう活用するか」といったことが重要です。
そのために、ICTツールを使いこなせる人材育成のための研修が必要です。
また、若手とベテランのITリテラシーには、経験に基づく知識の差や、新しい技術への適応、情報収集・活用方法に違いがみられます。
若手は新しい技術への関心度が高く、積極的に学習する傾向があります。
しかし、基礎的な知識や経験不足という側面も持っています。
これに対して、ベテランはこれまでの長い経験から得た知識やノウハウを持っており、トラブルシューティングに強いといった傾向が強く見られます。
けれども新しい技術への適応に時間がかかる場合があります。
こういったそれぞれの強みと弱みを理解し、互いに協力し合う事で、より高いITリテラシーの習得に繋がります。
これらのことを解決する場としても、研修の実施は非常に重要です。
まとめ:多職種が連携して支える「地域で生きる」社会へ
高齢化が進む現代社会において、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるようにするために、医療と介護の連携は不可欠です。
他職種が連携することによって高齢者が必要な医療と介護をスムーズに受けられるようになり、病気の治療だけでなく個々のニーズに合わせた日常生活のサポートや精神的ケアも同時に受けられるため、より自分らしい充実した生活を送ることが可能になります。
つまり医療と介護が連携することは、利用者のQOLの向上に直結します。
そして、これらを支えるケアマネジャー、医師、看護師など多種職が、まさに「連携の主役」と言えるのです。