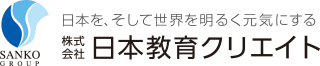ハラスメントを防ぐポイント
目次
こんにちは、クリエイト研修開発部です。
労働施策総合推進法が2019年5月に改正にされ、企業にはパワハラ対策が義務化されることになりました。今回の法制化によって、何か手を打たなければと感じている方も多いかと思います。
今回はハラスメントを防ぐ3つのポイントについてお伝えしようと思います。
ポイント1 グレーゾーンを知り、世代間の認識の違いを埋める
パワハラと認定される基準は昔と今とでは大きく変わってきています。パワハラのグレーゾーンについて理解し、日頃の行動を振り返ってみることが重要です。
「やる気がないなら、帰れ!」
この言葉はパワハラになるでしょうか?それともならないでしょうか?
答えはどちらの可能性もあるということです。それは状況や頻度によって変わってきます。ただ、もっと適切な表現があったとしたら、そもそも問題にならなかったのかもしれません。
グレーゾーンを知り、それを意識するとともに、自分たちの時代はこのくらい当たり前だったという認識を是正する必要があります。
ポイント2 「怒る」と「叱る」を分け、叱る技術を上げる
もう一つの問題は、パワハラを恐れて、何も言えなくなってしまうことです。
これでは、元も子もありません。
パワハラを防ぎ、かつ正常な組織運営をするには、育てる力を上げなければいけないのです。この「教える」「育てる」にも世代間の相違がでやすいものです。自分の教育、指示の出し方、指導について今一度振り返って確認することが求められます。
批判的、否定的だとパワハラと捉えられかねません。成長を願って肯定的に接する「コーチング」の力が昔以上に必要とされているのです。
ポイント3 受ける側の認知の変革、被害妄想に陥らせない
とはいえ、ちょっとした声がけをして、声をかけてきた相手に対してもともとネガティブな印象を持っていたためにハラスメントと感じてしまうという事が横行しては、上司もたまったものではありません。
受ける側の一定の倫理観やレジリエンス力も同時に育成する必要があります。
上司のちょっとした態度や行動を嫌味に感じ、それをそのまま放置すると必要以上に言動に過敏になり、被害妄想が膨らんでしまうこともあります。
こうなってしまうと、とても厄介。
人間関係のこじれは修復が難しいのです。これには部下の側にも、上司との関係性を万地面とする力が求められます。
上司の強みや弱み、価値観を理解していくことで言動を冷静にみられるようになっていくのです。これらは「ボスマネジメント(ボスとの関係性をマネジメントすること)」と言われ、研修内容としても人気が出てきています。
相手のことが「嫌い」という感情は「相手のことを理解していない」ということに起因することがほとんどなのです。
コミュニケーションの基本は相手との違いを理解することから。
「違う」→「理解できない」→「苦手」という負のスパイラルに気づくことで、人間関係のストレス軽減に繋がっていきます。
筆者紹介