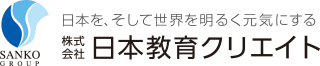キャリアデザインとは何か?少子高齢化・人材流動化に対応する戦略を考える
目次

はじめに
キャリアデザインとは、将来の自分のありたい姿や働き方を主体的に考えて、その実現に向けて計画を立て、行動していくことです。キャリアデザインが今注目されている理由、それは働き方の変化、個人の価値観の多様化、そして企業の人材戦略の変化が挙げられます。
終身雇用の崩壊、VUCA時代と呼ばれる不確実性の高まりによって自分のキャリアを自律的に設計する力を必要とする時代に変化しているのです。副業や人材流動化の進展、働き方が多様化する現代において、個人のキャリア形成における選択肢が広がり、企業も柔軟な人材活用を模索する動きがみられるようになるなどライフスタイルも多様化しています。
また、キャリアデザインの必要性を高める重要な社会要因として少子高齢化があります。労働力人口の減少や社会の変化に対応するため、個人は自律的なキャリア形成を意識し、企業はそれを支援する体制を整える必要があります。 こういった背景のもと、キャリアデザインは個人と企業の双方にとって重要です。
企業にとってもこれまでのように、新卒一括採用や終身雇用といった従来の雇用慣行に頼るだけでは、必要な人材を確保することが難しくなっています。
そのため、企業は従業員一人一人のキャリア自立を支援し、従業員が長く活躍できるような環境作りが求められています。
キャリアデザインとは何か
キャリアデザインの定義と目的
キャリアデザインの基本概念は、将来の理想像から逆算して人生と仕事を設計することです。将来の自分のありたい姿や働き方を主体的に設計し、その実現に向けて行動していくことを目指します。
キャリアデザインにおいての自己理解とは、自分の興味、価値観、強み、弱み、スキル経験などを深く理解することです。
また目標設定は、将来のキャリアを計画し、実現するための重要なプロセスです。目標を明確にすることで、日々の行動に一貫性がうまれ、より効果的なキャリアアップが可能になります。
目標設定には、長期的な目標と短期的な目標の両方を設定し、SMARTの法則(Specific、 Measurable 、Achievable 、Relevant、 Time-bound)に基づいて具体的に設定することが重要です。
行動計画は、理想のキャリアを実現するために具体的な行動を計画することです。目標達成のための具体的な行動計画をたて、自分のキャリアにおける目標や理想の状態を明確にし、現状とのギャップを把握します。次に目標達成に必要なスキルや経験をリストアップし、それを習得するための具体的な行動計画を立てます。
計画は、短期・中期・長期に分け、それぞれに具体的な行動目標を設定し、定期的に進捗状況を確認し、必要に応じて修正することが成功への鍵となります。 終身雇用制度の揺らぎやジョブ型雇用の増加、副業の解禁やフリーランスなど働き方の多様化、そして少子高齢化による労働力人口の減少や、人生100年時代の到来により、個人が主体的にキャリアを考えて長期的なキャリアプランを立てる必要性が高まっています。
キャリア形成・キャリアパスとの違い
キャリア形成とは、個人が仕事を通じて、自身の能力や経験を積み重ね、自己実現を追求するプロセスのことです。単に働くことだけではなく、将来の目標を明確にし、それに向かって計画的に行動していく事を指します。一方、キャリアパスとは企業が従業員に対して、将来どのような職務や地位に就くか、そのためにどういった経験やスキルを身につける必要があるのか、その道筋を示すものです。
つまり、企業が用意したキャリアアップのモデルや昇進・昇格のルートを示し、個人の主体的な選択や意思決定よりも、組織の都合やルールが優先される傾向があります。
そのため、キャリアデザインの方がより個人による意思決定と行動が重視されるため、主体的かつ戦略的な考え方と言えるのです。
キャリアデザインの5ステップ
キャリアアップを成功させるために、具体的に以下の5つのステップがあります。
ステップ1 自己理解
自分の性格、能力、スキル、価値観や関心などを可視化することで、客観的に現状の自分を分析し自己理解します。自己理解を深めることで、自分の強みや弱みを把握して、どのようなキャリアを築きたいか、どういった働き方をしたいのかなど、目標設定や行動計画を具体的に立てるための基盤となります。
自己理解は、キャリアデザインの最初のステップなために、とても大切です。この自己理解が不十分だと目標設定や行動計画も的外れになることが考えられます。
ステップ2 将来像の明確化
将来の明確化は、キャリアアップを目指す上で非常に重要なプロセスです。自己分析を通じて自分の強みや価値観、興味関心、キャリアの目標を理解することから始まります。自身のキャリアにおける理想の将来像を描き、それを実現するための現状とのギャップを把握します。そのギャップを埋めるための具体的な計画をたてることを指します。「どうなりたいのか」「どのような働き方をしたいのか」という将来像を5年後、10年後に合わせ、とのような自分になりたいかを、具体的に描くことがコツです。
ステップ3 目標設定と計画立案
将来像を実現するために、具体的な目標を設定します。そして目標達成に必要な行動を具体的に計画します。実用的な手法として以下のことが挙げられます。
① キャリアの目標を明確にする
② 現状を分析する
③ 具体的な計画行動を立てる
④ 行動計画を実行する
⑤ 行動計画を見直す
ステップ4 実行と習慣化
キャリアアップのための5つのステップを実行し、それを習慣化させることは、目標達成と自己成長を加速させるために重要です。実行とは、目標達成に向けた具体的な行動を起こすことで、習慣化とは、その行動を継続的に行う状態を指します。
この2つを組み合わせることで、計画的なキャリアアップが可能になります。実行と習慣化を成功させるためには、モチベーションを維持することが重要です。
その方法としてスモールステップがあります。これは大きな目標を小さなステップに分割します。そうすることでモチベーションを維持しやすくなります。行動を習慣化させるためのテクニックとして、毎日同じ時間、同じ場所で行動することが効果的で重要です。
また習慣化をサポートするツールや環境を活用することも必要です。習慣化の過程で、反抗期、不安定期、倦怠期などの段階があることを理解して、乗り越えるための策をたてることも必要です。
その中において、定期的に行動の結果を振り返り改善点を見つけていきます。成功体験を認識することでモチベーションを高め、失敗体験から学ぶことで次の行動に活かしていく、といった振り返りをすることがとても大切です。
ステップ5 修正・アップデート
キャリアデザインのステップにおける「修正」と「アップデート」は、ライフイベントや現状、環境変化に応じて計画を見直し、より効果的なキャリア形成を目指すことです。
具体的に言うと、修正とは現状のキャリアプランや目標が、想定していた状況や自信の変化と乖離してきた場合に、そのプランや目標を柔軟に見直し再検討や調整することです。
また、アップデートとは常に最新の情報を収集し、変化する状況に対応できるように、キャリアプランやスキルを常に最新の状態に保つことを指します。具体的に言えば、市場の変化への対応、スキルのアップデート、ネットワークのアップデートがあります。
キャリアデザインは、一度作成したらそれで終わりということではありません。常に変化する状況に対応し、柔軟に修正とアップデートを繰り返し見直していくのです。それによって、 より効果的なキャリア形成を実現できます。
医療関係職のキャリアデザイン
医療現場で求められるキャリア観
医療の現場において求められるキャリア観は、チーム医療・多種職連携・専門性の深化・対人スキル強化などが挙げられます。
具体的にいうと、医師、看護師、薬剤師などそれぞれの専門職が高度な知識やスキルを磨くことが求められます。その分野での専門性を深め、スペシャリストとして活躍することが期待されるのです。
医療は、医師、看護師、薬剤師、リハビリテーションスタッフなど、様々な専門職が連携して行う、チーム医療が基本となります。お互いの専門性を理解して円滑なコミュニケーションを図り、患者様の包括的なケアを提供するために協力することが不可欠です。
そこでは、患者様の価値観や意向を尊重することが重要です。また、患者様やご家族、同僚など様々な人とのコミュニケーションを取る必要があるために対人スキル強化として、コミュニケーション能力を高めていくことも大切です。患者様の状況を的確に把握し、わかりやすく説明する能力、他職種と円滑なコミュニケーションを図る能力が必要です。
事例紹介:看護師のキャリアデザイン
看護師のキャリアデザイン事例として、専門職を高める、管理職を目指す、教育・研究に携わる、起業するなど様々な選択肢があります。
具体的に言うと専門看護師や認定看護師の資格を取得し、特定の分野で活躍する、師長や主任などの管理職について組織の運営に携わる、或いは大学院に進学し研究を行う、起業においては訪問看護ステーションの立ち上げなどが挙げられます。その他、国際看護師として、海外での看護といった国際的な医療活動への参加や医療ソーシャルワーカーとして、患者様の生活をサポートすることで、社会復帰を支援するということもあります。
介護職のキャリアデザイン
介護職のキャリアパスとやりがいの再発見
介護職のキャリアパスは、一般的には介護職員初任者研修から始まり、介護福祉実務者研修を経て、介護福祉士の資格取得を目指します。取得後は、ケアマネージャーや施設長、認定介護福祉など、現場業務からリーダー職、相談員、管理職など成長に合わせ様々な方向で活躍することが可能です。
介護職のキャリアパスを考えるということは、仕事のやりがいを再発見する上でとても重要です。自分の強みや興味を確認し、理解した上で、目標を明確にすることで、これまで以上に充実した介護職人生を送ることに繋げられます。
介護業界特有のスキルアップ方法
介護業界でスキルアップをするために、資格の取得や研修受講、キャリアチェンジ、独立などの様々な方法があります。それらの一例を以下にご紹介します
資格の取得例:「介護福祉士」「介護支援専門員=ケアマネージャー」「認定介護福祉」 「認知症ケア専門士」
研修制度:「介護技術研修」「認知症ケア研修」「コミュケーションスキル研修」「ストレスマネジメント研修」「喀痰吸引研修」 キャリアチェンジ:「生活相談員」「サービス提供責任者」「管理者・施設長」「看護師」「理学療法士」
キャリアデザイン支援の取り組みとメリット
企業が支援することで得られるメリット
キャリアデザインを支援することは従業員と企業の双方にメリットがあります。
従業員にとっては、自分のキャリアプランを明確にすることで、仕事に対してのモチベーションアップや主体的な行動を促し、スキルやキャリアを高めることに繋がります。
一方、企業は離職率低下、従業員満足度の向上という面から人材の定着率の向上、従業員のエンゲージメントの向上、長期雇用による業務効率化や生産性の向上、その結果として組織全体の活性化へと繋がります。 これらのメリットは数値で表されることもあります。その数値例を以下に示します。
〇社員エンゲージメントの向上
ある調査で、キャリア支援のプログラムに参加した従業員のエンゲージメントスコアが、未参加の従業員に比べて平均15%アップという事例
〇定着率の向上
ある企業ではキャリアデザイン研修を導入した結果、離職率が10%低下
〇優秀人材の定着と獲得
ある調査では、キャリア支援制度が充実している企業は、そうでない企業に比べて、応募数が平均20%アップと結果
〇生産性向上
ある調査では、キャリアデザイン支援によって、生産性が平均10%アップという結果
サポート方法の事例紹介(面談・コーチング・研修)
これまでにも述べてきたように、キャリアサポートは従業員が自身のキャリアを主体的に形成できるよう、企業が提供する支援のことです。ここではその具体的な方法と事例をご紹介します。
① キャリア面談
定期的な面談を実施することで、従業員のキャリアに関する悩みや目標を把握します。
② キャリアコンサルティング
キャリアコンサルタントによる専門的なアドバイスを提供することで、キャリアプランの策定を支援します。
③ 研修プログラム
業務に必要なスキル、知識を習得できる研修プログラムを提供します。
自己啓発の促進のため、資格取得支援や学習制度を設けます。
キャリアデザイン研修の導入と効果
研修導入の背景とニーズ
キャリアデザイン研修を導入した背景には、終身雇用制度の崩壊や働き方の多様化といった、これまでのキャリアパスが通用しなくなったという現状があます。従業員がキャリアを描けないことによるリスクとして、モチベーションの低下、離職、組織全体のパフォーマンス低下などが考えられます。
こういった背景をもとに企業は、従業員が主体的にキャリア形成できるように、キャリアデザイン研修を導入し、支援していく必要性があるのです。
当社が提供する研修の特長と強み
日本教育クリエイトでは、医療・介護分野に特化した事例中心のプログラムをご用意しています。
現場のリアルな事例に合わせた内容をもとに、今後のキャリアに向けて何が必要なのか、自分で考えて行動する主体性を促します。職員の個性を応援し、なりたい自分になるための道筋を考える研修です。
明確な目標立てと行動プランで職員がいきいきと働くようになる、モチベーションアップ関連研修の「キャリア・デザイン研修」です。2025年6月に、現場の職員により身近なプログラムとして新たにリリースしたプログラム。ワークを中心に、受講生自身で答えを探し求める「超参加型」研修は、キャリアについて語り合い、「自己開示⇔他者の意見」による『新たな視点』の発見を導きます。
今後のキャリアを明確にし、具体的なプランを立てることで、持ちべーションアップや主体的な行動を実現する内容は、現代社会の背景をもとに作り上げられ、確実な効果が期待できます。
■研修案内はこちらから
介護事業所向けはこちら>>
医療機関向けはこちら>>
まとめ
キャリアデザインとは、将来の自分の姿や働き方を主体的に考えて、設計していくことです。
それは単に企業での昇進や昇給を目指すだけではなく、仕事やプライベートを含めた人生全体を視野に入れて計画を立てることです。現代における働き方の変化、個人の価値観の多様化、そして企業の人材戦略の変化を背景として、今とても注目されているのです。
少子高齢化の中、終身雇用が崩壊し、不確実性の高まるVUCAと呼ばれる時代、自分のキャリアを自律的に設計する力が必要となってきています。
働き方が多様化する時代、副業や人材流動化の進展、個人のキャリア形成における選択肢が広がり、企業にも柔軟な人材活用を模索する動きがみられます。
そのために、従業員一人一人が主体的にキャリアを描ける環境を整備することが重要です。キャリア支援は離職防止・人材育成・組織力強化に直結する施策です。
キャリアデザインを中長期的な経営戦略として捉えることは、企業と従業者双方にとって重様です。今こそ、制度整備・研修導入・面談強化など、キャリア支援に本気で取り組む好機なのです。