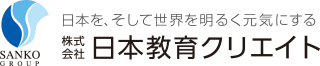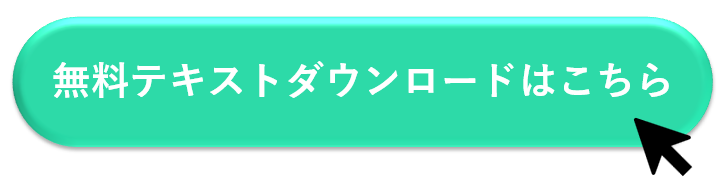ハラスメントの種類とその特徴:職場や社会でして知っておくべきハラスメント事例
目次
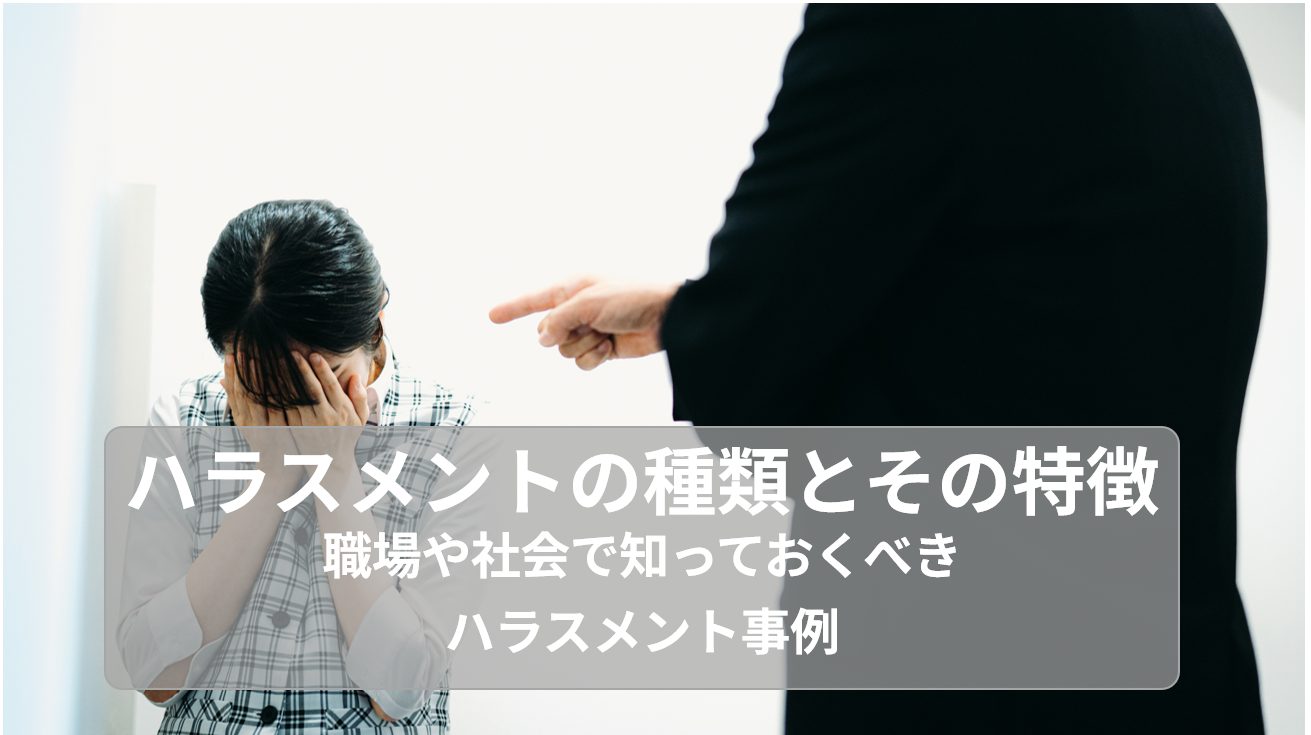
はじめに
ハラスメントの種類は多様化しており、今や50種類以上もあると言われています。
ハラスメントは増加傾向にあり、中でもよく起こるものとして
「パワーハラスメント」「セクシャルハラスメント」「モラルハラスメント」「カスタマーハラスメント」
が挙げられます。ここではこれらの概要を説明します。
ハラスメントとは?基本的な定義と理解
まずは、ハラスメントに関する基礎的な知識を得るところから始めましょう。
ハラスメントの意味とその背景
ハラスメントとは、「いやがらせ」「いじめ」「苦しめる」など相手を不快にさせる、脅す、尊厳を傷つける言動や言葉のことです。
相手がハラスメントと受け取る場合や、相手を傷つける意思がない場合においてもハラスメントとみなされます。
「セクハラ」は1980年代に社会問題として認識され、「パワハラ」は2000年代に入って問題視されるようになるなど、平成時代において一般用語として認識されて広まり、ハラスメントの種類は、様々具体化されていきます。
令和に入り益々社会問題として取り上げられているのです。
ハラスメントが社会に及ぼす影響
ハラスメントが起きると、以下のような悪影響が考えられます。
① 職員のメンタルヘルスの不調を引き起こす
② 退職者や離職者が増える
③ 職場環境が悪化することで生産性が低下する
④ 企業が法的に責任を問われる
⑤ 企業のイメージダウン
ハラスメントは被害者の尊厳及び人権侵害といったもの繋がる恐れがあります。
組織において、スタッフのモチベーションが低下し、離職や退職や裁判に至ったり、最悪なケースとして自殺に繋がるリスクがあることを認識しておくことが必要です。
職場におけるハラスメントの種類
ここでは、各種ハラスメントの種類とその定義をご紹介します。
パワーハラスメント(パワハラ)とは?
パワハラの定義は、上司が部下に対して職場内の立場や優越性を利用し、適正範囲を超えて不当な言動や指示・命令を与え、身体的・精神的苦痛を与え職場の環境に悪影響を及ぼすことを言います。
典型的な事例として、次の6類型があります。
① 精神的な攻撃
② 身体的な攻撃
③ 過大な要求
④ 過小な要求
⑤ 人間関係からの切り離し
⑥ 個の侵害
パワハラの防止策として企業や従業員が取るべき対策としては、次の5つのことが必要です。
① トップのメッセージ
② ルールを決める
③ 社内アンケートなで実態を把握する
④ 教育をする
⑤ 社内での周知・啓蒙
厚生労働省HP参照
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001018003.pdf
セクシャルハラスメント(セクハラ)
職場におけるセクハラの定義は、相手を不快にさせる性的な言動のことです。
それには「対価型」と「環境型」があります。
厚生労働省のHPを参照すると、例えば、次のようなものが挙げられています。
■「対価型」
労働者の意に反する性的言動に対して拒否・抵抗と言った労働者の対応により、
その労働者を解雇・降格・減給・契約更新拒否・不利益な配置転換など、不利益を受けることを言います。
具体例としては次のような事柄です。
① 事業主が組織内で労働者に対して性的関係を要求したが、拒否されたためその労働者を解雇する。
② 出張中の車中で、上司が労働者の腰や胸を触ったが、抵抗されたためその労働者に不利益な配置転換をする。
③ 組織内において事業主が日頃より労働者に関わる性的な事について公然と発言し、抗議されたたためその労働者を降格させる。
■「環境型」
労働者の意に反する性的な言動により、労働者の就業環境が不快になった為、能力の発揮に重大な悪影響が出るといった就業上、見過ごすことの出来ない程度の支障が生じることを言います。
具体例としては次のような事柄です。
① 組織内で上司が労働者の腰や胸などを度々触った為、その労働者が苦痛に感じ就業意欲が低下している
② 取引先に同僚が労働者に関する性的な内容の情報を意図的に継続的に流した、その労働者が苦痛に思い仕事が手につかない
③ 労働者が抗議しているが、同僚が業務に使用するPCでアダルトサイトを閲覧するため、それを見た労働者が苦痛に思い業務に専念できない
厚生労働省HP参照
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000378182.pdf
また、セクハラの発生状況は増加傾向にあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001259093.pdf
被害者の声として、セクハラを受けたと思っても上司と部下のという関係や状況を考え、自分から行動を起こせない、なかなか相談しづらいという現状があります。
男女雇用機会均等法第11条では、職場におけるセクシュアルハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001019259.pdf
モラルハラスメント(モラハラ)とは?
職場におけるモラハラの定義は、厚生労働省のこころの耳のHPによると、言葉や態度・身振り、文章などで働く人の人格や尊厳を傷つける行為。
肉体的・精神的に傷を負わせ、その人が職場を辞めざる得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせることとなっています。
モラハラの加害者について、次のような特徴が挙げられます。
① 自分の意見や行動が正しく、相手の意見を受け入れる余裕がない
② 他人の意見や気持ちを無視したりする
③ プライドが高く自分の間違いを認めない
④ 他人をうらやみ嫉妬する傾向にある
⑤ 権力・地位への欲求が強く自分を特別だと思っている
⑥ 支配欲が強い
⑦ 人として他者を尊重せずに、モノのように扱う
また、被害者には次のような特徴が挙げられます。
① 自己主張をするのが苦手
② 自分の思う意見を通すより他者の意見に合わせる人
③ 真面目で責任感が強い
④ 自分に自信を持てないタイプ
⑤ 素直な人
⑥ 罪悪感を持ちやすい人
⑦ 他人につくすタイプ
そして、職場においてのモラハラの兆候として、残業の強制、挨拶及びメールの無視、人格や能力を否定する発言、社内イベントなどへ出席させない、などが見受けられます。
そのため、日ごろから、モラハラは絶対に許さないという考えを組織内で共有する、相談形式をしっかり整えておくことが大切です。共通認識を持つために、すべてのスタッフへ研修を行うことが望ましいのです。
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?
職場におけるカスハラの定義は、顧客からの取引先からのな理不尽な要求や暴言・暴力といった攻撃、セクハラなどの行為を受けることです。
スタッフの対処法としては次のようなものが挙げられます。
① 相手の主張をよく聴き取り、記録する
② 不明点については「わからない」と言う
③ 警察へ連絡をとる
④ 相手の氏名・住所の確認
⑤ 理不尽な要求は受け流す
組織として、カスハラ対策のマニュアルを整えておくこと、組織内での相談体制を明確にしておくこと、カスハラを受けたスタッフへのケアをしっかり行うなどのサポートが重要です。
また、患者やご家族から受ける理不尽で社会通念上不相当なクレーム及び暴言・暴力・セクハラを受けることを、ペイシェントハラスメント(ペイハラ)といった、ハラスメントの種類です。これらに対処するためにも、組織としての方針の理解や対象方法の共通認識をスタッフ全員、持つことが必要です。そのための研修を取り入れることはとても有効です。
▼医療機関向けペイハラ研修の詳細はこちら▼
https://www.create-ts.com/iryou/training/harassment/customer/
▼介護事業所向けカスハラ研修の詳細はこちら▼
https://www.create-ts.com/kaigo/training/harassment/customer/
マタニティハラスメント(マタハラ)とは?
妊娠や出産、育児を理由にして、女性が職場で受ける理不尽な扱い嫌がらせのことです。
例えば、妊娠したことを理由に退職を要求する、育児休業を拒否する、妊娠・出産の休みによる同僚からのいじめ、早い時間に帰りづらい雰囲気などが挙げられます。
マタハラは、「労働基準法」や「男女雇用均等法」「育児・介護休業法」で守られている権利を侵害するものであり、違法です。
そのため、相談窓口の設置・マタハラを禁止する旨を就業規則に掲げる・マタハラに関するマニュアル作り・マタハラ相談者への研修を行うなど、組織としてマタハラの防止対策を講じる義務があります。
ジェンダーハラスメントとは?
性別に基づく差別的な発言や行動、嫌がらせなどの不当な行動のことです。
例えば、「女のくせに」「男らしくしろ」と言った発言や、「家事や育児は女がするもの」「男は仕事を優先するべき」「女性は育児で休むため昇進は出来ない」などが相当します。
そのため組織として、ハラスメントを禁止する旨の規定を明確にし共通認識を持たせる、相談窓口を設置する、発生時の対応策を整えておく、研修を実施するなどが重要です。
社会や家庭で見られるハラスメントの種類
ハラスメントが発生するのは職場だけではありません。生活の様々な場面で発生しうる問題です。
アカデミックハラスメント(アカハラ)とは?
大学や大学院などの教育機関において、研究者や学生が教授や指導者からの不適切な扱いを受けることです。
例えば、学習や研究活動の妨害や指導義務の放棄、卒業・進級の妨害、指導の差別、研究成果を収奪するなどが挙げられます。
対策として、大学などの相談窓口での相談、弁護士への相談、事実をメモで残すなどの対応策があります。
また、アカハラは民法709条「不正行為による損害賠償」に該当する違法行為です。
ドメスティックハラスメント(ドメハラ)とは?
家庭内において、パートナーを支配する為に心理的・物理的な暴力を含むもので、DV(ドメスティックバイオレンス)の一種です。
テレワークが普及し、家族が一緒にいる時間が増えたことでの家庭内での摩擦が増えたことなども一因となり、社会問題になっています。
近しい友人などへの相談で解決できない場合は、公的な相談支援センターなどの相談窓口や民間の弁護士会の相談窓口、カウンセラーなど専門家に相談することで解決策を検討します。
エイジハラスメント(エイハラ)とは?
年齢や世代を理由とした、差別的な言動や嫌がらせをすることです。
例えば、シニアスタッフが体力的にもまだまだ仕事はしっかり出来て、意欲も高いながら、シニアという理由だけで希望を却下する、世代を一括りにしてしまうことや、「おじさん」「おばさん」というような、その年齢を強調して表現する呼び方をすることが当てはまります。
パワハラやセクハラといったハラスメントの種類とは違い、まだ多くの人に知らせていないという問題がある中、悪気無く無意識に使用するスタッフがいるという現状。
組織内でエイハラについての認識を広めることが対応策として必要です。
スモークハラスメント(スモハラ)とは?
職場や公共の場で、喫煙者が非喫煙者にたばこの煙やにおいを受動喫煙させてしまうことで、精神的・肉体的に嫌な思いをさせてしまうことです。
喫煙及び受動喫煙は健康被害を生じます。
そのため希望しない喫煙や受動喫煙はハラスメントに該当するのです。
組織として、喫煙場所を設置する、喫煙者へ禁煙のサポートをする、喫煙のルールを明確にするスタッフへの教育といった対策が必要です。
SNSやオンラインでのハラスメント
実生活(オフライン)の世界だけでなく、オンライン上でもハラスメントは発生します。
オンラインハラスメントとは?デジタル社会のおける新たな脅威
ハラスメントの種類にはSNSやメールなどオンライン上での中傷や嫌がらせをするものあります。
自宅といった個室など周りから見えない状況で行われるという特徴があるため、その行動がどんどんエスカレートしていくリスクがあります。
サイバーハラスメントの実例と対策
SNSやメール、チャットなどオンライン上で個人攻撃や誹謗中傷、嫌がらせをする行為です。
例えば、嘘のプロフィールを公開したり、仲間外れにする、屈辱的な写真や動画を流す、悪い噂話を広めたりすることが該当します。
加害者が匿名なことが多いので、追及するのが難しい特徴があります。
組織において、スタッフに対してネット利用のリスクの周知を行うことや、組織や仕事に関するSNS投稿へのルールを明確にするなどの対策が必要です。
また侮辱罪にあたる場合には刑事責任に問われる可能性もあります。
テクノロジーハラスメント(テクハラ)の概念と対応策
IT機器などテクノロジーの発展に伴い、それらを苦手とする人々に対するいじめやいやがらせのことで、ハラスメントの種類の中でも新しい形のものです。
組織の対策として、先ずはテクハラについて理解をさせることが重要です。
またITに関しての研修を行うなども必要不可欠です。
組織内のマニュアルを整え使いやすいツールを使用する、また、テクハラが起きた際の対応策を明確にしておくことも重要です。
ハラスメントに関する法律と企業の責任
ハラスメントについては法律においても取り組みを行うことが定められています。
日本のハラスメントに関する法的規制とは?
法律規制には、次の物が挙げられます。
① 労働施策総合推進法
② 男女雇用機会均等法
③ 育児介護休業法
④ 労働契約法
⑤ 民法・刑法
これらを基に、それぞれの様子に応じて適切な法令が適用されます。
また、被害者には以下の法的権利があります。
① 加害者に対する損害賠償請求権
② 会社に対する損害賠償請求権
企業のハラスメント防止義務と取り組み
企業には、法的にハラスメントの防止措置を講じることが義務化されています。
2020年6月1日施行 「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」
規模を問わず全ての事業主に適用されます。
例えば、パワハラ防止措置として、相談窓口を設置や産業医と連携してフォローする、就業規則で規定することや相談者において不利益な扱いを行わないなどが挙げられます。
導入事例として、厚生労働省HPにおいて「職場での働きかけと継続的な取り組み」け「毎年アンケートを実施」「継続的な研修実施」などを紹介しています。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000178025.pdf
まとめ
雇用や就業形態も変わり、価値観も多様化した複雑な現代社会において、ハラスメントの種類も様々に多様化しています。
ハラスメントは人格権の侵害であり許されるものではありません。
個人として、組織として、社会全体でハラスメントにつての共通認識・知識をしっかり持つことが必要です。
日ごろから、発生を想定した対応策を明確に整え、発生時には適切に迅速に対応することが重要です。
日本教育クリエイトでは、医療・介護業界向けにハラスメント対策のための研修を行っています。
是非、ご活用ください。
▼医療機関向けハラスメント研修の詳細はこちら▼
https://www.create-ts.com/iryou/training/harassment/harassment.php
▼介護事業所向けハラスメント研修の詳細はこちら▼
https://www.create-ts.com/kaigo/training/harassment/harassment.php
テキスト無料ダウンロードもございます。
現場での勉強会やご自身での学習にぜひご活用ください。