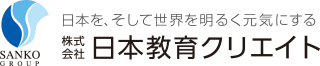傾聴力とは?職場で欠かせないコミュニケーションのポイントを解説
目次
傾聴力とは?職場で欠かせないコミュニケーションのポイントを解説

傾聴力とは、相手の話に真剣に耳を傾け、理解しようとする能力のことで、職場や日常のコミュニケーションにおいて重要なスキルです。傾聴力を身に付けることで、相手の信頼を獲得したり、チームの関係性が良くなったりと、様々なメリットがあります。
本稿では、傾聴の実践方法や習得の仕方について解説します。
傾聴力とは?
傾聴力は、相手の話を聴く力が重要なカウンセラーに必要なスキルとして、アメリカの心理学者カール・ロジャースが提唱したものです。
しかし、今や傾聴力はカウンセリングの場を超え、ビジネスの場においても重要視されています。特に医療・介護の現場では、職員同士・対患者・対利用者におけるコミュニケーションスキルとして、必須のスキルとなっています。傾聴力とはそもそもどんなスキルなのでしょうか。
傾聴力は相手を理解する力
傾聴力とは、相手の話に身を入れて真剣に耳を傾け、深く聴きとる力のことです。英語では「Active Listening(アクティブ・リスニング)」と言われています。Active(アクティブ)と表される通り、積極的に相手の話を聴くことが重要です。
傾聴力には、相手が発した言葉の意味を理解するだけでなく、相手の表情や声のトーン等、言葉以外の要素にまで注意を払い、本当に伝えたいことを引き出す力ということまで含まれます。
傾聴力のスキルを活用することによって相手との信頼関係が生まれ、円滑なコミュニケーションや良好な人間関係をもたらします。
傾聴力の3要素
傾聴力を提唱したアメリカの心理学者カール・ロジャースによると、傾聴には下記の3要素が必要であるとしています。
■共感的理解
相手の話を相手の立場に立って気持ちに共感しながら、理解する姿勢のことです。その際には、相手が話す内容について「おそらくこう思っているのではないか?」と推測したり、決めつけたりしてはなりません。ましてや、相手の話を止めて「こういうこと?」と質問したりするのも良くないです。相手が何を感じているのかを、寄り添いながら理解しようとすることが重要です。
■無条件の肯定的関心
相手の価値観や人格を否定せず、好き嫌いの評価を入れずに聴くことです。そのためには、相手の話を聴くときに自分自身の偏見や先入観を持たず、「なぜそのような考えに至ったのか」など、肯定的に相手の話をとらえて聴くことが重要です。
■自己一致
相手に対して真摯な態度で対応することです。もっと具体的に述べるならば、相手の話を聴いているときに、「感じていること」と「相手への言葉・態度」が一致していることです。
例えば、相手の話があまりよくわからず、理解できていないにも関わらず「わかります~」と言っても真実味が無く、相手からの信頼を得ることはできません。話が分かりにくい時は、分かりにくいことを相手に伝え、理解できるよう努力することが重要です。聴き手側が自己開示をすることで、相手も自身の心と向き合えるようになります。
傾聴力が職場で求められる理由
ビジネスシーンにおいても、重要なスキルとして傾聴力が求められています。職員が傾聴力を身に付けることは、ビジネスにおいてどのようなメリットがあるのでしょうか。
職場のチームワークが良くなる
職員同士が真摯な態度や相手を尊重する姿勢で接し合うことで、お互いを信頼し合うようになり、チームワークが良くなる効果が見込めます。コミュニケーションの改善を図ったところ、お互いに連携が取れるようになり、業務効率が上がったという例もあります。
顧客との信頼関係を構築することができる
傾聴力は職員同士のみならず、顧客に対しても役立ちます。傾聴によって顧客が安心感を持って話しをしてくれるようになるため、より相手のニーズを聞き出したり、相手の深いところまで理解できるようになったりします。結果として顧客との良好な信頼関係が構築できるようになり、リピートの獲得や、その顧客からの紹介による新規顧客獲得といったことも期待できます。
人材の定着につながる
職員の離職の多くは、人間関係によるものです。上記のように、職場の環境が良くなったり、顧客とも信頼関係を築くことができるようになったりすると、人間関係での悩みが軽減され、人材の定着にもつながっていきます。
傾聴の際に意識すべき6つのポイント
傾聴をする際に意識すべき6つのポイントをご紹介します。
<ポイント1>聴く態度と姿勢を意識する
傾聴力においては、相手の話を聴く態度や姿勢も重要な要素になります。
例えばパソコンを見ながら、何かの作業に集中しながらなど、相手の話を聴いているのかどうかわからない態度や姿勢では、相手も話をする気が失せてしまいます。
意識的に体をしっかりと相手に向け、目や顔を見るようにすることで真剣さが相手に伝わり、相手も話をしてくれるようになります。
<ポイント2>ミラーリング(同調効果)を意識する
「相手と飲み物を同じタイミングで飲んだ」「相手と同時に同じことを言った」等の出来事によって、相手に親近感を覚えた経験は無いでしょうか。
ミラーリングとは、自分と同様の仕草や行動をする人に好感をもつ心理効果のことです。相手と同調することで、親密感や安心感を与えることができます。
例えば、相手と同じタイミングで座る、相手がうなずいたら自分もうなずく、相手が身振り手振りで説明したことについて同じことをする、などがミラーリングにあたります。やりすぎだったり不自然な感じになったりして、相手に不快感をあたえてしまうのは良くないですが、相手の話をしっかり聴こうという心構えや姿勢があれば、これらは効果的なものとして相手に印象付けられます。
<ポイント3>バックトラッキング(オウム返し)を意識する
バックトラッキングとは、相手の言葉を活用して、言葉を返していくコミュニケーションの進め方です。
例えば、
相手:「この前久しぶりに野球観戦に行ったんだ!」
私:「へ~!野球観戦に行ったんだー!」
このような会話です。
話す側からすると、相手が自分と同じ言葉を使ってくれることで、「否定されていない」「受け入れてくれている」という感覚を覚えます。つまり、バックトラッキングは相手の抵抗感を打ち消し、肯定的な感覚を与えることができる、という効果があると言えます。
<ポイント4>ペーシング(相手に合わせる)を意識する
ペーシングとは、言葉や言葉以外の要素を含めて相手に合わせ会話を進めるという技法です。「相手が声を抑えているときはこちらも声を抑えて話す」「相手がゆっくり話しているときはこちらもゆっくり話す」「相手が結論から話すタイプの場合はこちらも結論から話す」など、相手の声のトーン、話すスピード、話し方などに意識的に合わせることで、相手に安心感や親近感を持たせることができます。
<ポイント5>会話の割合を意識する
傾聴においては、相手と自分が話す割合も重要です。
例えば面談において、部下の話を色々聴こうと思っていたが、ついつい自分の話ばかりしていた、という経験はありませんか。
傾聴においては、自分よりも相手のほうがたくさん話をしている、という状況が理想的です。目安としては、相手と自分の話す割合が「相手7:自分3」くらいになるように調整するとよいでしょう。
<ポイント6>相手に共感しながら話を聴く
先にも述べた通り、傾聴においては、相手の話を否定せずに受け入れて理解することが重要です。
「でも…」「私はそう思わない」「それは理解できない」などの否定的な言葉を使ったり、怪訝そうな表情などで否定が態度に表れていたりすると、相手は話す気がなくなってしまい、相手の本当の気持ちや考えを知ることができなくなってしまいます。共感的理解が相手の親近感や安心感につながる、ということを良く意識しましょう。
傾聴力を身につける方法
ビジネスにおいて様々なメリットがある傾聴力というスキルですが、何をすれば身に付けることができるのでしょうか。
結論から申し上げますと、上記の6つのポイントを意識しながら、実際に会話をしてトレーニングを積めば身に付けることができます。傾聴力について知識はあったとしても、実践できるとは限りません。ポイントを意識しながら、実際に会話を重ねていくことで、徐々に自分の身になっていきます。その際に、客観的に見て今の傾聴の姿勢は適切かどうか、第三者的な目線からのフィードバックがあるとよりよいです。
以下、傾聴力を高めるためのトレーニング方法をご紹介します。
日常会話で実践する
仕事やプライベート含め、傾聴を意識しながら日常会話を行うということも、傾聴力を鍛える効果的な取り組みになります。家族や友人などと会話をするときに、傾聴ができていたかどうか振り返ってみると、自分のできていなかったことが見えてくるかもしれません。
ロールプレイングの実施
理論や知識の習得とあわせて、実践的な練習を行なうことで、現場で役立つ傾聴力が身につきます。特に新人や業界経験の浅い職員の場合、現場で患者様やご利用者とのやり取りを行うようになる前に、十分なロールプレイングで練習をすることで、自信をもって現場に出られるようになります。
研修を受ける
職員間の連携強化、職員同士の関係性改善など、職場全体で傾聴力を高めることで現状の課題を解決したい場合は、職員に向けて研修の機会を設け、傾聴のトレーニングを行うことが効果的です。もしそのような研修を行ったことが無い場合は、ぜひ一度検討してみてください。
当社では、医療機関・介護事業所向けのコミュニケーション研修を行っております。
ぜひ研修導入に際して、一つの参考としてご覧ください。
医療機関向けコミュニケーション研修はこちら>
介護事業所向けコミュニケーション研修はこちら>
コミュニケーション研修のサンプルテキストを入手できます
メールアドレスだけの簡単入力でテキストをGETする>
まとめ
傾聴力は、ビジネスの場において重要なスキルとして認識され、様々な良い効果をもたらします。専門知識・課題解決力・論理的思考力など、習得が難しいものに比べると、傾聴力の習得はハードルが低いものではないでしょうか。トレーニングの機会があれば誰でも習得可能です。職場全体の傾聴力向上によって、働きやすいよい職場づくりを実現しましょう。